DIRECTOR'S STATEMENT

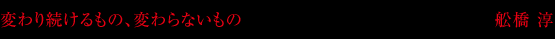
ニューヨークに10年間住んだのち、私は母国へと戻り、東京の谷中と呼ばれる地域に住み着いた。寺社と墓地に埋め尽くされた静かな下町になんとなく惹かれたのがその理由だった。「寺と坂の町」と呼ばれる谷中は、本郷と上野の二つの台地に挟まれた谷であることがその地名の由来といわれている。私は大都会東京の喧噪の深部にありながら、墓石と寺に埋め尽くされ、いつもしんとしているこの「谷」にひかれた。そこを貫く路は言問(こととい)通りと呼ばれ、谷はまるで言霊の漂う此岸と彼岸の間のようにも感じられた。
ニューヨークからの荷を解き、いざ谷中に腰を下ろしてみると、そこは江戸以前から長らく続く伝統工芸職人が、ひっそりと暮らす昔ながらの下町だと言うことを知った。墓石の仏名を記す書の職人や、お面や纏(まとい)作りの名人、江戸宮大工の棟梁など、資本主義経済の中でそのニッシュを見失うことなく、手工芸を守り抜いてきた方々だった。
日本人でありながら余所者である私は、語りかけると気さくに応じてくれる彼らとの対話を楽しむようになった。谷中霊園にある天王寺五重塔の史跡を知ったのも、そこで郷土史家・加藤勝丕さんと出遭ったのがきっかけだった。彼はライフワークとして町の人々と一緒に五重塔再建運動を進めているという。昭和32年7月6日、つまり50年以上も前に焼けて失われた塔をなぜ今更再建しようとするのか、この素朴な疑問を出発点として私の興味と想像力は膨らみ始めた。
私は幸田露伴著「五重塔」を読んだ。明治25年(1892)資本主義が立ち上がりつつある日本で、「順々競争の世の中」つまり競争社会では徳の高い人物は正当に評価されず不遇に遭う、そんな社会への批判を込めた傑作だ。技術はあるが、渡世が下手でいつも小さな仕事ばかりしている大工十兵衛が、江戸では誰もが認める棟梁源太に楯突き、周囲の批判、揶揄を受けながらも、美しい欅作りの仏塔を建立するというストーリーだが、この十兵衛が体現している価値観=名誉でも金でもなく、塔に身を捧げんとする精神性が、現代の谷中人(やなかびと)が五重塔を懐古する想いにどこか通底しているようにも感じられた。
しかし、人はただ古いものを懐かしんでいるだけなのだろうか?昨今谷中の観光地化が進み、週末になるとデジタルカメラ片手に路地歩きを楽しむ人口が増えている。昭和レトロブームに便乗し、美しい国日本、ふるさと観光といったキャッチフレーズが連呼され、下町・谷中が商業主義に消費されゆく。閉塞感漂う現代日本への不安が、過去への郷愁へ人々を駆り立てているのだと分析する知識人も多い。外部からの観光客と地元の人の想いに差はあるだろうが、いずれにせよ谷中の路地に人が惹きつけられるのは、懐かしさだけではないように思えた。
おそらく人は、時代がめまぐるしく変化する中で何が変わり、何が変わらないのか、感じ取りたいという知的欲求に突き動かされているのではないだろうか。例えば、三軒長屋は殆ど姿を消し、近代建築に取って代わられているという変化がある一方、谷中の路地を住民が所狭しと沢山の鉢植えで粋に彩っているという光景は変わらない。谷中霊園にはもはや五重塔は立っていないが、墓地へ彼岸に人がお参りに訪れるという姿は変わらない。行き交う人々のファッションが変化し、自動車の交通量も多くなったが、情緒ある谷中の坂を下り、上ってゆくという情景は変わっていない。
私は「谷中暮色」で、現代において形骸化したものを見つめることで、過去の精神性を浮き上がらせたいと思った。五重塔の礎石、家族が集まる法事、昭和32年に撮影されたフィルムなど、形だけは残っているものの本質、精神性がもはや消失しているものをキャメラで見つめてみようと思った。それは、五重塔が焼け落ちた1957年(昭和32年)という過去、幸田露伴「五重塔」の作品世界である江戸時代中期という大過去へと想像力を飛翔させ、時代劇のフィクションへと結びついた。大過去、過去、現代と3つの時代の映像の記憶を往復することで、時間と共に変わったもの、変わらぬものがより鮮明に浮き上がってくるのではないかと思えたのだ。
温故知新といえば単純だが、映画においては「温新知故」もありうる。現代と向き合うことで、過去の価値が見えてくるということだ。今あれほど懐かしがられている五重塔の礎石をみて、過去の五重塔へ想いを馳せたり、今恋に落ちる男女を見つめながら大過去に妻夫を契った若者へ想像力を羽ばたかせたり。すると、現代よりも過去がよりヴィヴィッドに、より生き生きと我々の脳裏に浮き上がってくるのではなかろうか。
現代の若者と同じほど若い大工十兵衞は、世間や親方に押さえつけられ、否定されたのにも関わらず、立派な五重塔を作り上げた。それが後世になるともはや伝統として権威ある文化財となってしまう。伝統とは時代と共に「変わり続ける価値」であり、それを「変わらぬ伝統」であると信じる人間の「変わらぬ性質」がそこにある。